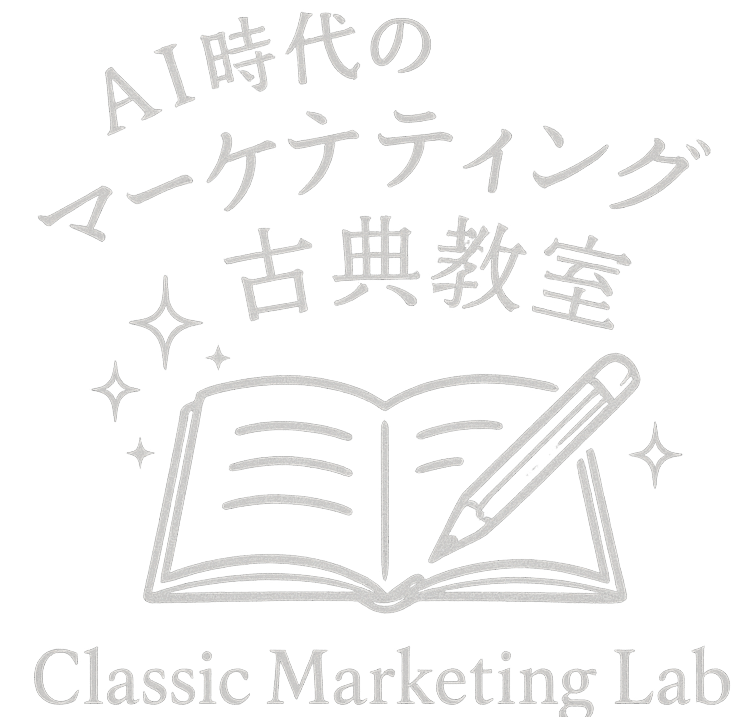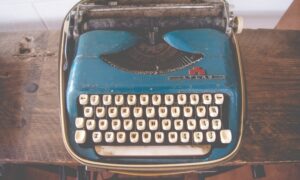こんにちは。AIという言葉をテレビやインターネットでよく耳にするようになりましたね。AIの中でも、特に注目されているのが「ChatGPT」です。まるで人間と話しているかのように、色々な質問に答えてくれるすごいAIです。
AIがどんどん賢くなる時代に、「人間の考える力」はもう必要ないのでしょうか。実は、そんなことはありません。AIがどんなに進化しても、最終的に物事を決めたり、新しいアイデアを生み出したりするのは、私たち人間です。
そして、AIを上手に使うためには、「どんな質問をするか」がとても大切になります。今回は、ChatGPTを使って何か計画(戦略)を立てるときに、つまずきやすい「問いかけ方」と、どうすればもっと良い答えを引き出せるのかを、中学生の皆さんにも分かりやすくお話しします。
目次
- AI時代に「問い」の力が大切な理由
- ChatGPTが苦手な「あいまいな問い」
- よくある「間違った問い」と、その対策
- 「良い問い」を作るための3つの魔法のコツ
- 実例でチャレンジ: 最高の文化祭を計画しよう
- AIを使いこなす「人間の思考力」とは
- まとめ: ChatGPTは、あなたの最高のパートナー
AI時代に「問い」の力が大切な理由
ChatGPTのようなAIは、インターネット上の膨大な量の情報を学習しています。まるで、世界中の図書館にある本を全部読んで、そこに書かれていることを全部覚えているようなものです。だから、私たちが何か質問をすると、その知識の中から、一番良いと思われる答えを探し出して教えてくれます。
しかし、AIは「考える」というよりも、「与えられた情報の中から最もらしい答えを生成する」のが得意です。私たちがどんなに素晴らしい道具を持っていても、その道具の使い方が分からなければ、良い結果は生まれませんよね。
例えば、料理ロボットがあるとします。このロボットに「おいしい料理を作って」とだけ命令しても、どんな料理を作るべきか、どんな材料を使うべきか分からずに困ってしまいます。でも、「冷蔵庫にある鶏肉と野菜を使って、中学生が喜ぶような簡単でおいしい献立を3つ考えて。調理時間は30分以内ね」と具体的に伝えれば、ロボットはきちんと役立つアイデアを出してくれるでしょう。
これと同じように、ChatGPTも、私たちが「どんな問い」をするかによって、引き出せる答えの質が大きく変わるのです。あいまいな質問では、あいまいな答えしか返ってきません。しかし、的確で具体的な質問をすれば、期待以上の素晴らしいアイデアやアドバイスをもらうことができるのです。
AIがどんどん私たちの生活に入ってくる中で、AIを上手に操り、自分の目標達成に役立てる力。これこそが、これからの時代に求められる「人間の考える力」の一つなのです。
ChatGPTが苦手な「あいまいな問い」
ChatGPTは、とても賢いですが、私たち人間が当たり前に持っている「常識」や「空気を読む力」は持っていません。私たちが「なんとなく」思っていることを察してはくれないのです。
たとえば、友達に「なんか面白いことないかな?」と聞けば、相手はあなたの好きなものや最近の出来事を考えて、何か提案してくれるかもしれません。でも、ChatGPTに同じ質問をしても、「面白いこと」という言葉があまりにも広すぎて、何を答えていいか分からなくなってしまいます。マンガの紹介が良いのか、ゲームが良いのか、それともお笑い芸人のネタが良いのか、AIには判断できないのです。
このような「あいまいな問い」をしてしまうと、ChatGPTは無難な答えや、あなたが本当に知りたいこととは違う答えを返してくることがあります。まるで、宝探しで「どこかに宝物があるよ」とだけ言われて、地図もヒントももらえないような状態です。これでは、いつまでたっても宝物を見つけることはできません。
だからこそ、私たちはChatGPTに「もっと良い答え」を出してもらうために、聞く前に少し立ち止まって、「どう聞けば、AIは一番良い答えを出してくれるだろう」と考える必要があるのです。これが「問いの設計」です。
よくある「間違った問い」と、その対策
では、実際にChatGPTを使うときに、どんな「問いかけ方」が間違いやすいのでしょうか。よくある4つのパターンと、それぞれの対策を見ていきましょう。
対策1: 「漠然とした問い」は具体的に
間違った問いの例: 「良い戦略を教えてください。」
なぜダメなの?
「良い戦略」といっても、何についての戦略なのか、誰にとって良いのかが全く分かりません。AIは何万通りもの「良い戦略」を知っているかもしれませんが、どれがあなたにとっての「良い」なのかは判断できないからです。
どうすれば良い?
「何について」の戦略なのか、「誰のため」の戦略なのか、もっと具体的に伝えることが大切です。
良い問いの例: 「新しくクラスで運動会に向けてチームを組むことになりました。クラス全員が楽しめるように、どんな戦略を立てたら良いですか。特に、運動が苦手な子も活躍できるようなアイデアが欲しいです。」
このように具体的に伝えることで、AIは運動会の企画、チーム分け、練習方法など、具体的な提案をしてくれるようになります。
対策2: 「情報不足の問い」にはヒントをあげる
間違った問いの例: 「学校祭を成功させるにはどうすればいい?」
なぜダメなの?
学校祭といっても、どんな規模の学校祭なのか、目的は何なのか、使える予算はどれくらいなのか、どんな出し物をするのかなど、AIが判断するための情報が足りません。情報が足りないと、AIは一般的なことしか答えられず、あなたにとって本当に役立つアイデアは出てきません。
どうすれば良い?
AIが考えるための「ヒント」として、現在の状況や目的、使える資源や制約などを教えてあげましょう。
良い問いの例: 「私の学校は全校生徒500人の中学校です。今年の学校祭のテーマは『未来』で、予算はクラスで2万円です。クラスで出し物を企画するのですが、お客さんが体験できるような、記憶に残る楽しい企画にしたいです。どんなアイデアがありますか?」
必要な情報をAIに与えることで、AIはあなたの状況に合った具体的なアイデアを提案しやすくなります。
対策3: 「単純すぎる問い」は多角的に
間違った問いの例: 「テスト勉強は、夜と朝どっちが良いですか?」
なぜダメなの?
この問いは「AかBか」という二択になっています。しかし、物事には良い面も悪い面もあり、どちらか一方が常に正しいとは限りません。AIも、どちらか一方を断定的に答えるのは得意ではありませんし、あなたの状況に合わない答えを出してしまう可能性があります。
どうすれば良い?
一つの視点だけでなく、複数の視点から考えてもらうように促しましょう。メリットとデメリット、違う選択肢なども聞くと良いです。
良い問いの例: 「テスト勉強について相談です。夜に勉強するのと朝に勉強するのでは、それぞれどんなメリットとデメリットがありますか。また、私のように夜は眠くなりがちで、朝は早く起きるのが苦手な生徒には、どんな工夫ができますか?」
このように問いかけることで、AIは多角的な視点から情報を提供し、あなたに合った対策を考えるヒントをくれるでしょう。
対策4: 「丸投げの問い」は一緒に考える姿勢で
間違った問いの例: 「夏休みの宿題を全部考えてください。」
なぜダメなの?
これは、AIに「あなたの代わりに全てをやってほしい」という「丸投げ」の問いです。ChatGPTは、答えを生成できますが、あなたの思考力を育てることはできません。また、倫理的な問題もあります。AIはあくまでツールであり、あなたの「思考のパートナー」として使うべきです。
どうすれば良い?
まずは自分で考えてみて、その考えをAIにぶつけ、さらに良いアイデアがないか、足りない部分はないかを質問するような姿勢が大切です。AIを「壁打ち相手」のように使うと良いでしょう。
良い問いの例: 「夏休みの自由研究で、地元の川の環境問題について調べようと思っています。いくつかアイデアがあるのですが、もっと良い調べ方やまとめ方がないかアドバイスが欲しいです。例えば、『川の水をきれいにする方法』と『川に住む生き物の変化』のどちらが中学生にとって取り組みやすいテーマでしょうか。また、地域の専門家へのインタビューは有効でしょうか。」
自分で考えたことをAIに伝え、さらに深掘りする。このやり方で、あなたの考える力もAIの力も、両方活用することができます。
「良い問い」を作るための3つの魔法のコツ
ここまでで、どんな問いが良くないのか、そしてどう改善すれば良いのかが少し分かってきたでしょうか。ここからは、どんな場面でも使える「良い問い」を作るための3つの魔法のコツを紹介します。
コツ1: 「5W1H」を使って詳しく話す
「5W1H」とは、「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(誰が)」「What(何を)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」の頭文字を取った言葉です。これらを意識して質問に含めることで、あなたの問いは一気に具体的になります。
- いつ: いつまでに必要なのか、時期はいつなのか
- どこで: どこで行うのか、場所はどこなのか
- 誰が: 誰に向けてなのか、誰が実行するのか
- 何を: 何を達成したいのか、どんな内容なのか
- なぜ: なぜその計画が必要なのか、目的は何か
- どのように: どんな方法で進めたいのか、どのような形式で回答が欲しいのか
これらの要素をできるだけたくさん問いの中に入れることで、ChatGPTはあなたの意図を正確に理解し、より適切な答えを出すことができます。
コツ2: 「ゴール」をはっきり伝える
あなたがChatGPTに何を求めているのか、最終的にどんな結果を得たいのかを明確に伝えましょう。
例えば、「学校の文化祭の出し物アイデアをください」ではなく、「学校の文化祭で、クラス全員が協力できて、来場者も笑顔になるような、体験型の出し物アイデアを3つ提案してください。予算は1万円以内、準備期間は2週間です」のように、最終的な目標や条件をはっきりと伝えるのです。
ゴールが明確であればあるほど、AIはそこにたどり着くための最短ルートや、効果的な方法を考えてくれます。
コツ3: 「役割」や「視点」を変えて聞いてみる
ChatGPTに「あなたは何の専門家として答えてほしいか」という「役割」を与えたり、「誰の視点」で考えてほしいかを伝えたりすると、より専門的で深い回答が得られることがあります。
例:
- 「あなたは有名な料理研究家として、冷蔵庫の残り物で作れる簡単レシピを教えてください。」
- 「あなたは中学校の先生として、生徒がもっと授業に集中できるような工夫を提案してください。」
- 「クラスの代表になったつもりで、文化祭で成功するためのリーダーシップについてアドバイスをください。」
- 「お客さんの視点から見て、この文化祭の出し物は楽しめると思いますか。改善点はありますか。」
このように、AIに特定の役割や視点を与えることで、AIはよりその専門性や立場に合わせた情報を提供してくれます。これは、まるで色々な分野のプロに相談しているような感覚で、多角的な意見をもらうことができるので、とても有効な方法です。
実例でチャレンジ: 最高の文化祭を計画しよう
ここまで学んだことを使って、実際にChatGPTと一緒に文化祭の戦略を考えてみましょう。
ダメな問いかけの例
あなた: 「文化祭で出し物のアイデアをください。」
ChatGPT: 「文化祭の出し物ですね。例えば、お化け屋敷、カフェ、劇、展示などがあります。どんなものが良いですか。」
→ これでは漠然としすぎて、当たり障りのない答えしか返ってきません。
良い問いかけのステップ
ここからが本番です。AIと「対話」しながら、一緒に最高のアイデアを作り上げていきましょう。
ステップ1: まずは状況と目的を伝える
あなた: 「私は中学校3年生です。今年の文化祭でクラスの出し物を企画しています。テーマは『未来への挑戦』です。クラス全員が役割を持って協力し、来場者(他の生徒や保護者)が笑顔になるような、少し驚きのある体験型の出し物を考えています。予算はクラスで2万円、準備期間は1ヶ月です。何かアイデアを5つ提案してもらえますか。」
ステップ2: ChatGPTからの提案を受けて、さらに深掘りする
ChatGPT: 「承知しました。『未来への挑戦』をテーマにした体験型の出し物アイデアを5つ提案します。
- VR未来体験ゾーン: 未来の学校や街をVRで体験できるコーナー。
- AIと未来予測カフェ: 来場者の簡単な情報からAIが未来の職業や趣味を予測し、ドリンクを提供。
- 未来型スポーツチャレンジ: ドローンやプロジェクションマッピングを使った新感覚スポーツ体験。
- タイムカプセル作成ブース: 来場者が未来の自分へメッセージを書き、タイムカプセルに。
- ロボットプログラミング体験: 簡単なロボットをプログラミングして動かす体験。
あなた: 「ありがとうございます。VR未来体験ゾーンとAIと未来予測カフェに興味があります。特に、VR未来体験ゾーンについて、具体的にどんな内容にすれば、来場者が『未来だ!』と感じて、感動してもらえるでしょうか。必要な機材や予算内でできる工夫も教えてほしいです。」
ステップ3: さらに具体的な課題を相談し、解決策を考える
ChatGPT: 「VR未来体験ゾーンですね。感動してもらうためのポイントは…(具体的な内容を提案)…必要な機材としてはVRゴーグルが複数台とPC…予算2万円で工夫するなら、スマホVRゴーグルと無料アプリの活用、背景はクラスで手作りする…」
あなた: 「なるほど。スマホVRゴーグルは良さそうですね。でも、クラスにVRゴーグルを持っていない子もいます。どうすれば、全員が楽しめるようにできますか。また、準備期間が短いので、クラス全員で分担して作業できるように、役割分担のアイデアも欲しいです。」
このように、AIが答えを出したら、それに対してさらに質問を重ねていくことで、どんどんアイデアが具体的になり、課題の解決策も見えてきます。まるで、優秀な先生や先輩に相談しながら、一緒に計画を練っているような感覚です。
ChatGPTの答えをどう活かすか
ChatGPTは素晴らしいアイデアを出してくれますが、それを「本当に実行できるか」「自分たちのクラスに合っているか」を最終的に判断するのは、私たち人間です。
AIの提案をそのまま受け入れるのではなく、
- 「このアイデアは本当に面白いだろうか」
- 「クラスの皆で協力できるだろうか」
- 「予算や時間内にできるだろうか」
- 「もっと良い方法はないだろうか」
AIを使いこなす「人間の思考力」とは
AIがどんなに進化しても、AIは「何をすべきか」を自分で決めることはできません。目的を設定したり、計画を立てたり、アイデアを評価したり、最終的な判断を下したりするのは、常に私たち人間です。
例えば、料理ロボットが最高のレシピを提案してくれたとしても、実際に「このレシピで作ろう」と決めるのは人間です。材料を買いに行くのも、火加減を調整するのも人間が関わります。
AI時代の「人間の思考力」とは、
- 「どんな課題を解決したいのか」を明確にする力
- 「AIにどう尋ねれば、最高の答えを引き出せるか」を考える力
- AIが提案した答えの中から「本当に良いもの」を見つけ出す力
- AIの答えを参考にしながら、自分なりの「より良いアイデア」を生み出す力
- そして、最終的に「どう行動するか」を決める力
まとめ: ChatGPTは、あなたの最高のパートナー
ChatGPTは、正しい使い方を知っていれば、あなたの勉強や趣味、将来の夢を考える上で、最高のパートナーになってくれます。まるで、どんな質問にも答えてくれる、とても賢い家庭教師や、あなたのアイデアを一緒に考えてくれるブレーンがいるようなものです。
今回ご紹介した「問いの設計」のコツをぜひ試してみてください。
- 漠然とした質問ではなく、具体的に伝える
- 情報を惜しまず、ヒントをたくさんあげる
- 一つの答えだけでなく、色々な角度から考えてもらう
- AIに丸投げせず、一緒に考える姿勢を持つ