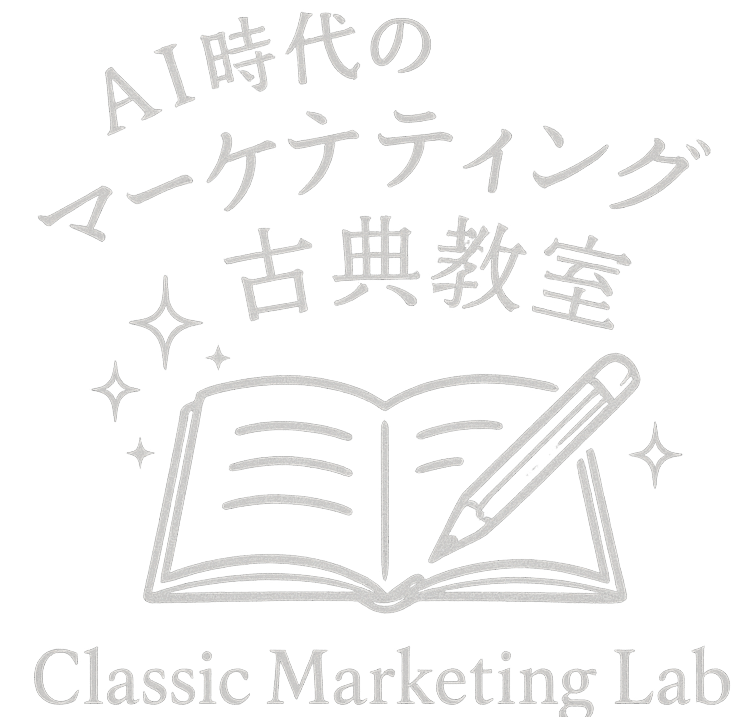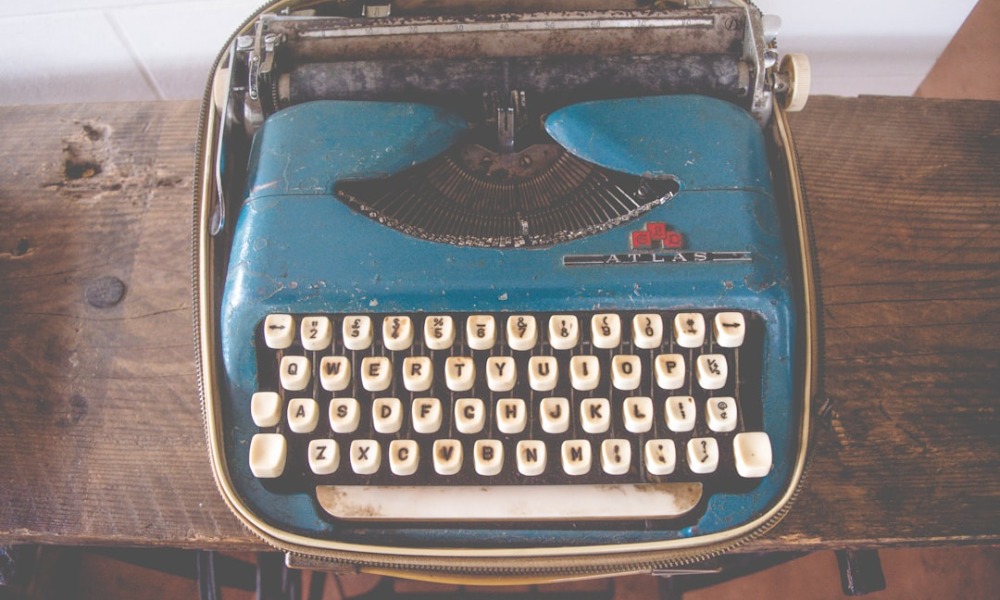こんにちは。AIがどんどん進化して、色々な文章をあっという間に作ってくれる時代になりましたね。でも、そんな時代だからこそ、人間が持っている「考える力」がすごく大切になります。特に、人の心を動かす文章、つまり「コピー」を作る技術は、これからの時代もずっと役立つ強力な武器になります。
今回は、昔から使われている広告の工夫を学びながら、人の心を「注意」「関心」「欲求」という3つの段階に分けて考えるすごい技を紹介します。これは、文章を作るだけでなく、人とのコミュニケーションやプレゼンテーションなど、色々な場面で役立つ考え方ですよ。
目次
- AI時代でも「人間の思考力」が最強の理由
- 昔の広告から学ぶ!心を動かす文章の秘密
- ステップ1:まずは「注意」を引く!あなたの目に止まるのは?
- ステップ2:次に「関心」を持たせる!もっと知りたいと思わせるには?
- ステップ3:そして「欲求」を高める!どうしても欲しくさせる言葉
- AIDMA(アイドマ)の法則とは?広告の歴史が生んだ偉大な考え方
- 現代のウェブマーケティングに活きる「注意・関心・欲求」の分解技法
- まとめ:AI時代を生き抜く、あなたの「思考力」を磨こう
AI時代でも「人間の思考力」が最強の理由
AIはすごいスピードで文章を作ったり、情報を集めたりできます。例えば、「夏休みの自由研究のテーマをいくつか考えて」とお願いすれば、AIは瞬時にたくさんのアイデアを出してくれるでしょう。しかし、AIは「人の気持ち」を完全に理解したり、「人の心を動かす」ような言葉を自ら生み出したりすることは、まだ得意ではありません。
私たちが今回学ぶ「注意」「関心」「欲求」を分解する技術は、まさに人の感情や行動を深く考える「人間の思考力」が必要です。どんな言葉で相手がハッとするか、どうすればもっと知りたいと思うか、そして最終的に「これだ」と感じてもらえるか。これは、AIが真似できない、私たち人間ならではの創造性や共感する力が求められる部分なのです。
だからこそ、このスキルを身につけることは、AI時代を賢く生き抜くための大切な力になるでしょう。
—昔の広告から学ぶ!心を動かす文章の秘密
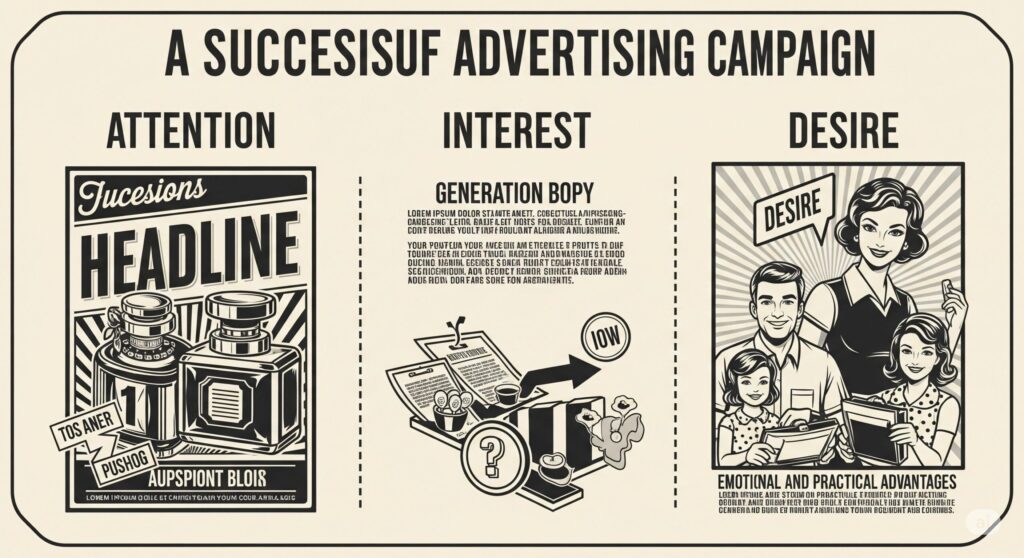
「コピー」とは、広告や宣伝に使われる短い文章のことです。例えば、テレビCMのキャッチフレーズや、雑誌の広告に書かれている商品紹介の文章など、たくさんのコピーが私たちの身の回りにあります。これらのコピーは、ただ商品を説明しているだけではありません。見る人の心を捉え、その商品を使ってみたくなるように工夫されているのです。
昔から、広告を作る人たちは、どうすれば人が商品を買いたくなるのか、どうすればサービスを使いたくなるのかを、一生懸命に研究してきました。その結果、「人は何かを知ってから、それが欲しいと思うまでに、いくつかの心の段階を通る」ということがわかってきたのです。この段階を、大きく「注意」「関心」「欲求」の3つに分けて考えてみましょう。
まるで、誰かに何かを売り込むときや、友達に自分の意見を聞いてほしいときに、いきなり本題に入るのではなく、まず「ねえねえ、聞いて」と注意を引いて、それから「実はね、こんな面白いことがあってさ」と関心を持たせ、最後に「だから、一緒にやってみない?」と誘うのと同じようなものです。
—ステップ1:まずは「注意」を引く!あなたの目に止まるのは?
人通りの多い商店街を歩いていると、たくさんのお店や看板が目に入りますよね。その中で、ふと「おや?」と立ち止まってしまうものがあるはずです。それが「注意を引く」ということです。広告の世界では、まず相手に「気づいてもらう」ことが何よりも大切になります。
日常にあふれる「注意を引く」工夫
- テレビCMの冒頭
CMの最初の数秒で、面白い音やインパクトのある映像、意外なセリフなどで、私たちの注意をグッと引きつけます。例えば、突然ユニークなキャラクターが登場したり、誰もが知っている歌がアレンジされて流れてきたりするCMは、思わず見てしまいますよね。 - 雑誌の表紙の見出し
本屋さんで雑誌を選ぶとき、たくさんの雑誌が並んでいます。その中で、「え、これ何?」と手に取ってしまうのは、目を引く大きな文字や、驚くようなキーワードが書かれているからです。「〇〇の秘密、ついに公開!」とか、「驚きのダイエット法」といった見出しがそれにあたります。 - SNSの流行りの動画
SNSで流れてくる動画も同じです。冒頭の数秒で「面白そう」と思わせないと、すぐにスクロールされてしまいます。意表を突く展開や、共感を呼ぶフレーズが、見る人の指を止めさせ、最後まで見させるきっかけを作ります。
コピーでの「注意」の引き方
コピーで注意を引くには、次のような方法があります。
- 問いかけでハッとさせる
「あなたの部屋、散らかっていませんか?」や「宿題、なかなか終わらないと悩んでいませんか?」のように、読み手の心に直接語りかける問いかけは、ドキッとさせて注意を引きます。自分に関係あることだと思わせるのがポイントです。 - 意外な言葉や数字を使う
「たった3日で人生が変わる方法」や「あの有名人も実は使っていた、驚きの〇〇」のように、常識を覆すような言葉や具体的な数字は、人の好奇心をくすぐります。聞いている人が「本当かな?」と疑問に思うことで、さらに読み進めたくなるのです。 - 問題提起で共感を誘う
「毎日のお弁当作り、もう疲れたあなたへ」や「朝起きるのがつらい…そんな悩みを解決します」のように、読み手が抱えている悩みや困り事を言葉にすることで、「私のことだ」と共感させ、注意を引きます。読み手は、その先に対策や解決策があることを期待して読み進めます。
注意を引くということは、たくさんの情報の中から「これはあなたにとって関係があることですよ」と教えてあげるようなものです。まるで、遠くから友達を呼ぶときに、まず大きな声で「おーい!」と声をかけるのと似ています。
—ステップ2:次に「関心」を持たせる!もっと知りたいと思わせるには?
無事に相手の注意を引くことができたら、次は「もっと知りたい」「面白そうだな」と思わせる「関心」の段階に進みます。せっかく振り向いてくれた相手に、すぐに飽きられてしまっては意味がありません。いかに興味を持続させるかが重要になります。
共感を呼ぶ「関心」の広げ方
- ドラマやアニメの続きが気になる
ドラマの次回予告や、アニメのエンディングで「続きは次回!」となると、「えー、早く来週にならないかな」とウズウズしますよね。これは、ストーリーの展開やキャラクターの成長に「関心」を持たせているからです。 - 友達の面白い話の続き
友達が「昨日さ、すごく変なことがあってね…」と話し始めたら、「何があったの?」と興味津々になりますよね。これは、話の展開や結末への期待から「関心」が生まれている状態です。
コピーでの「関心」の持たせ方
コピーで関心を持たせるには、注意を引いた後、その先の「メリット」や「面白さ」を具体的に示していくのが効果的です。
- 具体的な情報を加える
「たった3日で人生が変わる方法」で注意を引いたら、次は「この方法は、最新の心理学に基づいており、多くの成功者が実践しています。特に、時間の使い方が苦手な人には革命的です」のように、なぜその方法がすごいのか、誰に役立つのかといった具体的な情報を加えます。具体的な話は、興味を引きつけ、信頼感にもつながります。 - 読み手にとっての「得」を明確にする
「宿題が終わらない」という悩みに触れたら、「このアプリを使えば、毎日の学習時間が半分に減らせるかもしれません。空いた時間で、趣味や友達との時間に充てられますよ」のように、その商品やサービスを使うことで、読み手がどんな良い結果を得られるのかを具体的に示します。人は自分にとって良いことがあるとわかると、もっと話を聞きたくなるものです。 - 物語や事例を語る
「実際にこの方法を試した中学生のAさんは、テストの点数が20点アップしました」のように、具体的な人の成功例や、共感できる物語を語ることで、読み手は「自分にもできるかも」と感じ、さらに深く関心を持つようになります。物語は人の心を惹きつけやすい力を持っています。
関心を持たせるということは、相手が「へえ、もっと詳しく聞きたいな」「面白いね、それでどうなるの?」と感じてもらうことです。まるで、友達が話している面白いエピソードに「それでそれで?」と前のめりになって聞く状態と同じです。
—ステップ3:そして「欲求」を高める!どうしても欲しくさせる言葉
「注意」を引いて、「関心」を持たせたら、いよいよ最後の段階、「欲求」を高めます。「これは私にピッタリだ」「どうしても手に入れたい」「すぐにでも体験したい」と思わせるのが、この段階の目標です。
未来を想像させる「欲求」の生み出し方
- ゲームの新しいアイテムやキャラクター
「このアイテムを使えば、最強の敵を倒せるかも!」「このキャラクターがいれば、もっとゲームが楽しくなる!」と感じると、どうしても欲しくなりますよね。それは、そのアイテムやキャラクターを手に入れた未来を想像し、ワクワクするからです。 - テストで良い点を取ったときの気持ち
「この参考書を使えば、苦手な数学も克服できるかもしれない。そうなれば、次のテストで良い点が取れて、自信がつくぞ!」と想像すると、その参考書が欲しくなります。良い未来を具体的に想像させることが、欲求を高めるカギです。
コピーでの「欲求」の高め方
欲求を高めるコピーでは、読み手が商品やサービスを手に入れた後の「素晴らしい未来」を具体的に想像させることが重要です。
- 「ベネフィット」を強調する
「ベネフィット」とは、商品やサービスが提供する「良いこと」や「解決策」のことです。単に「速いスマホです」と言うのではなく、「このスマホなら、どんなに重いゲームもサクサク動いて、友達とのオンライン対戦も快適に楽しめるから、もっとゲームが面白くなるよ!」のように、使った結果、読み手が得られる「良い体験」を強調します。 - 限定性や緊急性を訴える
「今だけ!」「〇名様限定!」「〇日までの特別価格!」といった言葉は、買わないと損をする、今しか手に入らない、という気持ちにさせて欲求を高めます。人が行動するきっかけになることがよくあります。 - 成功した未来を具体的に描く
「この学習法を続ければ、志望校合格も夢じゃない。夏休み明けには、周りの友達をアッと驚かせることができるでしょう!」のように、その商品やサービスを使った結果、読み手がどうなれるのか、どんな素晴らしい未来が待っているのかを、まるで写真を見せるように具体的に描きます。読み手は、その未来を自分も手に入れたいと感じるようになります。
欲求を高めるということは、相手に「どうしてもこれが欲しい」「今すぐ手に入れたい」と思わせる強い感情を生み出すことです。まるで、喉がカラカラの時に目の前に冷たいジュースが出されたら、すぐにでも飲みたいと思うのと同じような状態です。
—AIDMA(アイドマ)の法則とは?広告の歴史が生んだ偉大な考え方
ここまで「注意」「関心」「欲求」の3つの段階を見てきました。実は、これらは広告の世界で昔から使われている有名な考え方の一部です。その代表的なものが「AIDMA(アイドマ)の法則」と呼ばれています。
広告が人を動かす流れの発見
AIDMAの法則は、約100年前にアメリカで提唱された、消費者が商品を知ってから購入するまでの心理的なプロセスを表したものです。
- Attention(注意):まず商品の存在に気づく
- Interest(関心):商品に興味を持つ
- Desire(欲求):商品が欲しいと思う
- Memory(記憶):商品を覚えている
- Action(行動):実際に商品を購入する
今回の記事で説明した「注意」「関心」「欲求」は、このAIDMAの法則の最初の3つの段階にあたります。残りの「記憶」と「行動」も合わせることで、人はどのようにして商品を買うまでに至るのかが、より分かりやすくなります。
この法則は、インターネットがない時代に考えられたものですが、今でもマーケティングや広告の基本的な考え方としてとても重要視されています。なぜなら、人間の心の動きというものは、時代が変わっても大きくは変わらないからです。
AIDMAの法則とインターネット時代
インターネットが普及し、情報があふれる現代では、AIDMAの法則に加えて、「AISAS(アイサス)の法則」というものもよく使われます。
- Attention(注意)
- Interest(関心)
- Search(検索):インターネットで情報を調べる
- Action(行動):購入する
- Share(共有):使ってみた感想をSNSなどで共有する
このAISASの法則では、「検索」と「共有」というインターネットならではの行動が加わっています。しかし、どちらの法則も「注意」「関心」「欲求(欲しいと思って検索する)」という最初のステップが非常に大切であることは共通しています。どんなに素晴らしい商品でも、まず知ってもらい、興味を持ってもらえなければ、その先の行動には繋がりません。
—現代のウェブマーケティングに活きる「注意・関心・欲求」の分解技法
私たちが今回学んだ「注意・関心・欲求」の分解技法は、現代のインターネットを使ったマーケティング、つまり「ウェブマーケティング」でも大いに役立ちます。ウェブサイトやSNSでの情報発信、ブログ記事の作成など、あらゆる場面でこの考え方を使うことで、より効果的に相手にメッセージを届けることができます。
ウェブサイトでの応用例
- トップページやランディングページ(LP)
ウェブサイトの入り口となるページでは、まず訪問者の注意を引くために、インパクトのある画像やキャッチフレーズを配置します。次に、その商品やサービスが「どんな問題を解決するのか」「どんな良いことがあるのか」を具体的に示して関心を持たせます。そして、最終的に「今すぐ購入」「資料請求」といったボタンを目立たせて、欲求からくる行動を促します。 - ブログ記事のタイトルと導入文
ブログ記事のタイトルは、まず読者の注意を引くための最も重要な部分です。「〇〇で失敗しないための5つのコツ」のように、読者の悩みや疑問に直接答えるようなタイトルにすると効果的です。導入文では、その記事を読むことで得られるメリットや、どんな情報が手に入るのかを伝え、読者に「もっと読みたい」という関心を持たせます。記事の途中で読者の悩みを深掘りしたり、解決策を具体的に示すことで、読者の欲求(解決したいという気持ち)を高めていきます。
SNSでの応用例
- 投稿の冒頭文やハッシュタグ
SNSでは、タイムラインを流れる情報量がとても多いので、最初の数行で注意を引くことが必須です。絵文字や記号を効果的に使ったり、「え、まさか!」「知ってた?」といった問いかけから始めるのも良い方法です。関連性の高いハッシュタグをつけることで、興味のある人に見つけてもらいやすくなります。 - 写真や動画と組み合わせる
目を引く写真や動画は、視覚的に注意を引く強力なツールです。その写真や動画に書かれたコピーで、さらに関心を引きつけ、「もっと知りたい」と思わせる情報を提供します。例えば、新商品の使い方を動画で見せたり、楽しそうに使っている人の様子を映したりすることで、見ている人の欲求を刺激し、「私も使ってみたい」という気持ちにさせます。
このように、「注意」「関心」「欲求」の分解技法は、形を変えながらも、現代のデジタルな世界でも非常に有効な考え方として使われています。どんなに技術が進歩しても、人の心を動かすための基本的な心理は変わらないのですね。
—まとめ:AI時代を生き抜く、あなたの「思考力」を磨こう
AIがどんなに進化しても、最終的に「人の心を動かす」のは、人間の役割です。今回学んだ「注意」「関心」「欲求」を分解する技術は、単に広告を作るためのものではありません。
- 友達に自分の考えを伝えるとき
- 発表会でみんなの注目を集めたいとき
- 家族に何かお願いするとき
- お店でアルバイトをするときにお客様に商品を勧める場面
など、日常生活の様々な場面で応用できる、大切な「考える力」です。相手が何を求めているのか、どうすれば相手が動いてくれるのかを深く考えることで、あなたのコミュニケーション能力は格段にアップするでしょう。
ぜひ、身の回りにある広告やお店のメッセージ、テレビCMなどを見るときに、「これはどうやって私の注意を引いているんだろう?」「何に関心を持たせようとしているんだろう?」「どうして欲しくなるんだろう?」という視点で見てみてください。そうすることで、あなたはAI時代でも輝ける、素晴らしい「思考力」を身につけることができるはずです。
この分解技法を、ぜひあなたの日常生活やこれからの学びの中で活用してみてくださいね。