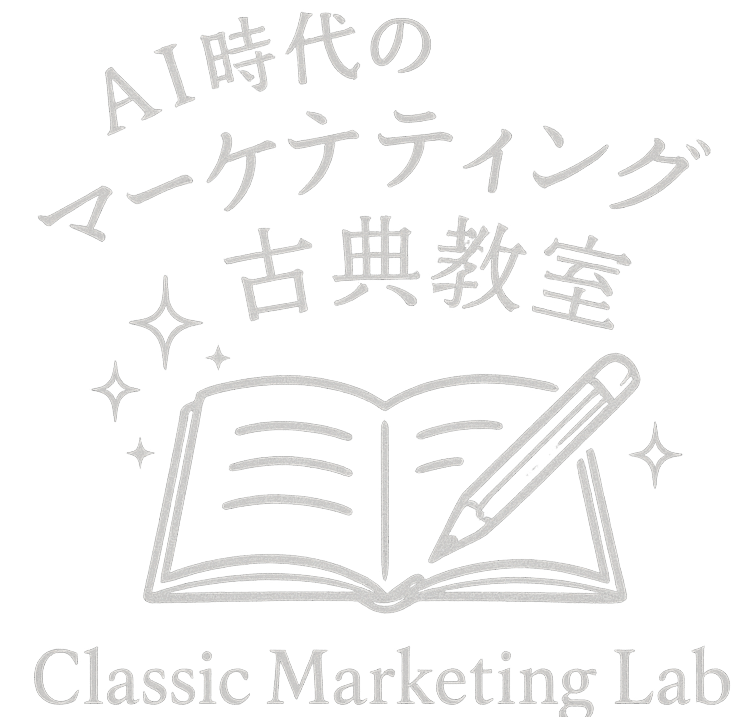昨日、元部下と久しぶりに食事をしたんです。彼は今では別の会社で開発部門のリーダーを務めているのですが、その成長ぶりに本当に感動しました。相変わらずエンジニアとしては優秀だし、最新のAIツールも使いこなしている。でも彼が言ったんです。「最近は採用や教育も任され始めたけど、プログラミングより難しいです」って。
その言葉を聞いて、ああ、これは今のリーダーが抱える共通の悩みなんだなと思いました。
人には、感情がある。
それをコントールすることは難しい。
そして、改めて私が若い頃に学んだ「感情に訴えかける」マーケティングの重要性を改めて実感したんです。
目次
AIがどんなに進化しても、人間の感情を理解し、心を動かすのは難しいと言われています。データや論理だけでは測れない「感情」こそが、消費者の購買意欲を大きく左右するからです。特に、情報が氾濫する現代において、いかに消費者の心に深く刺さるメッセージを届けるかは、マーケティングの永遠の課題ですよね。
今回、タイムマシンに乗って訪れたいのは、今から30年ほど前の「1990年代のTVCM」です。この時代は、まだインターネットが普及しておらず、テレビが「一家に一台」の主要メディアでした。だからこそ、CMには莫大な予算が投じられ、クリエイターたちは知恵を絞って人々の心を掴もうとしました。
「え、90年代のCMなんて今さら古くない?」と思うかもしれません。しかし、AIがどれだけデータ分析をしても、「人の心」を理解する上で、90年代のCMには今も色褪せないヒントが隠されています。なぜなら、この時代のCMは、理屈ではなく、感情に訴えかける「エモーショナルマーケティング」の宝庫だからです。
実は私も、誰もが知ってるあのCM「もっと〜、もっと〜」で有名な大手企業のWebサイトを手掛けたことがあります。その時に痛感したのは、テレビCMで築いた感情的な繋がりを、デジタルの世界でも継承することの難しさでした。データは完璧でも、心に響かない。その経験が、今回の記事を書くきっかけにもなっています。
この記事では、90年代の象徴的なTVCMを実例として挙げながら、なぜそれらが人々の心を捉え、記憶に残り続けたのか、その「感情訴求」の秘密を解き明かします。そして、AI時代だからこそ、私たちが学ぶべき「人間の思考力」で勝つマーケティングのヒントを探っていきましょう。中学生にもわかるように、わかりやすく解説していきます。
90年代ってどんな時代だった? 〜TVCMが「王様」だった頃
90年代は、日本経済が「バブル崩壊」という大きな転換期を迎えた時代でした。前半はバブル景気の余韻が残り、消費意欲も高かったですが、後半になるにつれて不況感が漂い始めます。しかし、そんな中でもテレビは圧倒的な影響力を持つメディアでした。
今のようにYouTubeもSNSもなかったため、多くの人が同じ時間に同じCMを見ていました。つまり、CMはただの商品紹介ではなく、社会のムードや価値観を映し出す鏡であり、人々の感情を揺さぶるエンターテイメントでもあったのです。
企業は、自社の商品やサービスを売るだけでなく、CMを通じて「どんなライフスタイルを提供したいのか」「どんな価値観を大切にしているのか」を伝えようとしました。そして、そのメッセージの多くは、論理よりも「感情」に強く訴えかけるものでした。
例えば、
- 「家族の絆」や「親子の愛情」を描いた感動的なCM
- 「友情」や「青春の輝き」を表現した爽やかなCM
- 「夢」や「希望」を抱かせるような壮大なCM
これらは90年代のCMによく見られた感情訴求のテーマです。消費者はCMを見て、「ああ、こんな風になりたいな」「こんな気持ち、わかるな」と共感し、商品やブランドに良いイメージを抱きました。そして、そのイメージが購買行動につながっていったのです。
なぜ今、90年代の感情訴求CMが注目されるのか? 〜AI時代の「心」の価値
AIは、膨大なデータを分析し、ターゲット層の年齢、性別、購買履歴、Web閲覧履歴などから、「この人はどんな商品に興味があるか」「どんな広告を見せれば購入する確率が高いか」を予測できます。これは非常に強力なツールです。
しかし、AIが苦手なことがあります。それは、人間の複雑な「感情」を深く理解し、創り出すことです。AIはデータを元に「悲しい」「嬉しい」といった感情を識別できますが、「なぜその感情が生まれたのか」という背景にある人間の繊細な心理や、「人の心を本当に動かす表現」を生み出すことは、まだ難しいのが現状です。
例えば、「感動的な物語」は、単に悲しい要素と嬉しい要素を組み合わせればできるものではありません。登場人物の葛藤、時間の流れ、音楽、言葉の選び方など、様々な要素が複雑に絡み合い、初めて人の心に深く響くものです。
90年代のCMは、まさにこの「人の心」に焦点を当てて作られていました。データが少なかった時代だからこそ、クリエイターたちは人間の洞察力と感性を最大限に活用し、普遍的な感情のテーマを追求しました。
AIがどれだけ進歩しても、「感情」は人間だけが持つ、かけがえのない価値です。そして、その感情を理解し、共感を呼ぶメッセージを生み出す能力こそが、AI時代に私たちが磨くべき「人間の思考力」なのです。
90年代TVCMの実例から学ぶ「感情訴求」の技
それでは、具体的な90年代のTVCMを見ていきましょう。これらのCMが、どのようにして人々の感情に訴えかけ、記憶に残り続けたのかを探ります。
実例1:JR東海「そうだ 京都、行こう。」シリーズ (1993年〜)
このCMシリーズは、90年代を代表するCMの一つであり、現在も続いています。
感情訴求のポイント:「憧れ」と「郷愁」
- CMは、京都の美しい四季の風景と、ゆったりとした時間が流れる情景を映し出します。そこに流れるのは、独特の静かなナレーションと、叙情的なBGMです。
- 「そうだ 京都、行こう。」というキャッチコピーは、まるで心の声のように語りかけ、見る人に「ああ、こんな場所に行きたいな」「非日常を味わいたいな」という憧れを抱かせます。
- また、古都の風景は、多くの日本人にとってどこか懐かしい、原風景のような郷愁の感情を呼び起こします。
- CMは、JR東海という交通手段を直接的にアピールするよりも、「京都への旅」という体験そのものの魅力を最大限に引き出し、見る人の心を旅へと誘いました。
実例2:サントリー「モルツ」 (1990年代)
「うまいんだな、これが。」というキャッチコピーで一世を風靡したモルツのCM。
感情訴求のポイント:「共感」と「幸福感」
- CMでは、仕事終わりに仲間と飲むビール、あるいは家族と過ごす休日の食卓など、日常のささやかな「幸せの瞬間」が描かれました。
- 「うまいんだな、これが。」という言葉は、大げさな表現ではなく、本当に美味しいものを飲んだときの、思わず漏れるような本音を表しています。見る人は、「ああ、わかるわかる」「私もこんな瞬間を味わいたい」と共感しました。
- ビールを飲むという行為が、単なる喉の渇きを潤すことではなく、一日の疲れを癒し、大切な人との時間を楽しむという幸福感と結びつけられました。
実例3:日清食品「カップヌードル」 (1990年代)
「hungry?」の問いかけと共に、奇抜な設定や独特な世界観で視聴者を驚かせたカップヌードルのCM。
感情訴求のポイント:「驚き」と「非日常」
- このシリーズは、それまでの食品CMの常識を打ち破る、まるで短編映画のような作りでした。SF、ファンタジー、歴史など、毎回異なるテーマで、見る人の想像力を刺激しました。
- 「なんだこれ?」「続きが見たい」と思わせるような驚きと、日常を忘れさせるような非日常の体験を提供しました。
- 商品そのものの美味しさを直接的に伝えるのではなく、その商品の周りに広がるユニークな世界観や、食べることで得られる解放感、あるいは単なる食事ではない「体験」を訴えかけました。
実例4:タンスにゴン (1990年代)
「ゴンゴンゴンゴン、タンスにゴン」という耳に残るフレーズと、可愛らしいキャラクターが登場するCM。
感情訴求のポイント:「安心感」と「親近感」
- 防虫剤という、どちらかというと地味な商品を、キャラクターを介して親しみやすく伝えました。
- 「衣類を守る」という商品の機能だけでなく、「大切なものを守りたい」という消費者の心理に寄り添い、使うことで得られる安心感を強調しました。
- 子供にもわかりやすい繰り返しフレーズと、キャラクターの愛らしさで、商品への親近感を抱かせ、家庭の中に自然と溶け込むような存在として認知させました。
感情訴求CMから学ぶ、AI時代のマーケティングヒント
これらの90年代CMの成功事例から、私たちはAI時代を生き抜くマーケティングのヒントを学ぶことができます。
ヒント1:「心のポジション」を狙う
90年代のCMは、単に商品の機能やスペックを伝えるだけでなく、消費者の心の中に「どんな体験を提供したいのか」「どんな気持ちになれるのか」という「心のポジション」を築こうとしました。
- JR東海は「旅の憧れ」というポジション
- モルツは「日常の小さな幸せ」というポジション
- カップヌードルは「非日常の驚きと自由」というポジション
- タンスにゴンは「大切な衣類を守る安心感」というポジション
これらは、AIがデータ分析だけで見つけ出すのが難しい、人間の深い感情や潜在的な欲求に根ざしたものです。AIは効率的なターゲティングや情報収集をサポートしてくれますが、「どんな心のポジションを狙うのか」という戦略的な思考は、やはり人間の役割です。
ヒント2:ストーリーテリングの力
90年代のCMは、多くの場合、短いながらもストーリーがありました。主人公がいて、感情の起伏があり、見る人が登場人物に共感したり、自分を重ね合わせたりできるような工夫が凝らされていました。
ストーリーは、単なる情報の羅列よりもはるかに記憶に残りやすく、感情に訴えかける力があります。AIはストーリーの骨格を作ることはできますが、本当に人の心を揺さぶるような、共感性の高いストーリーを生み出すには、まだまだ人間の創造性や経験が必要です。
あなたの会社の創業ストーリーや、商品開発の裏話はありませんか?お客様があなたのサービスを使って、どんな風に人生が変わったか、という感動的なエピソードはありませんか?データだけでは語れない「物語」こそが、AI時代に強いマーケティングの武器になります。
ヒント3:五感に訴えかける表現
90年代のTVCMは、映像、音楽、ナレーション、効果音といった様々な要素を巧みに組み合わせ、見る人の五感に訴えかけました。例えば、モルツの「うまいんだな、これが。」という言葉は、ビールの泡立つ音や、グラスに注ぐ音、そして飲む瞬間の表情と相まって、視覚だけでなく聴覚、そして味覚にまで訴えかけました。
Webマーケティングでも、ただ文字を並べるだけでなく、写真、動画、音声、そしてWebサイトのデザインや操作性など、様々な要素を組み合わせて五感に訴えかける工夫ができます。AIは素材の選定や最適化をサポートしてくれますが、それらを「どう組み合わせれば、人の心が動くか」という感性は、人間の領域です。
AIを「相棒」にして、「心」で勝つマーケティングへ
AIの登場は、マーケティングの世界に大きな変化をもたらしました。データ分析や自動化によって、これまで人間が時間をかけていた作業の多くが効率化されるようになりました。
しかし、90年代のTVCMが教えてくれるのは、「効率化」だけでは届かない「心」の領域があるということです。
AIは、あなたのターゲット顧客の分析、競合の動向把握、効果的な広告の配信など、様々な面で強力な「相棒」になってくれます。しかし、そのAIが生み出したデータや分析結果を元に、
- どんな「心のポジション」を狙うのか
- どんな「ストーリー」で感情を揺さぶるのか
- どんな「五感に訴える表現」で記憶に残すのか
という戦略を立て、クリエイティブな表現を生み出すのは、依然として人間の役割です。
AIは、私たちマーケターがより「人間らしい」仕事に集中できる時間を与えてくれます。データ分析に時間を割く代わりに、顧客の感情を深く理解し、心に響くメッセージを創り出すことに時間を費やせるのです。
まとめ:古くて新しい「感情訴求」の力
90年代のTVCMは、約30年の時を超えて、私たちに「感情訴求」の重要性を教えてくれます。情報過多の現代において、消費者は単なる機能や価格だけでは動かされません。彼らは、商品やブランドを通じて、「どんな感情を味わえるのか」「どんな体験ができるのか」を求めています。
AIがどれだけ賢くなっても、普遍的な人間の感情、そしてその感情を揺さぶるストーリーや表現を生み出すのは、私たち人間ならではの強みです。
AI時代だからこそ、私たちは「一番」になれる場所を見つけ、90年代のCMのように「感情」に訴えかけるメッセージを、WebやSNSを通じて発信していくべきです。
あなたの会社の商品は、お客様にどんな感情を届けたいですか?
あなたのサービスは、お客様にどんな物語を提供したいですか?
AIを賢く使いこなしながら、人間の感性で心を動かすマーケティングを実践し、AI時代を勝ち抜く力を身につけていきましょう。